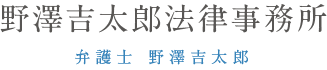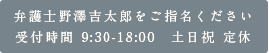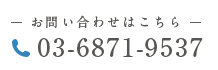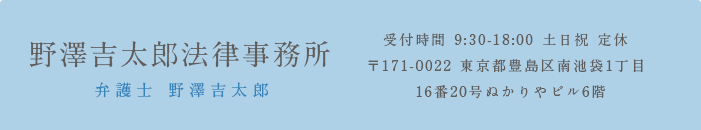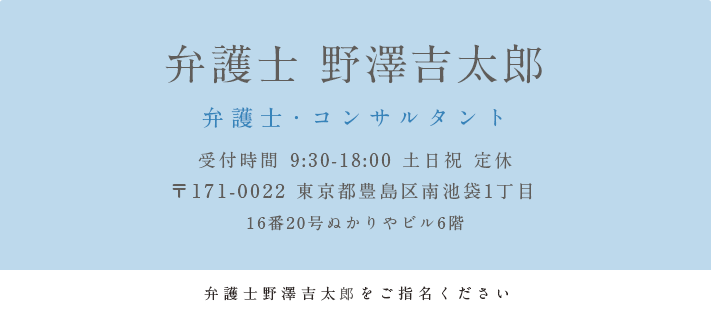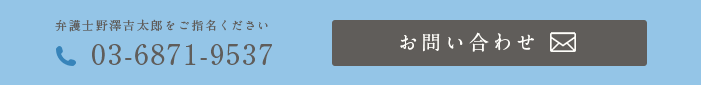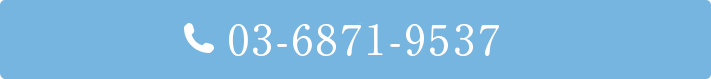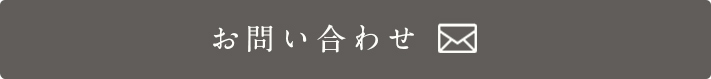法人設立ワンストップサービス(その10)~労働基準監督署
2023.10.17更新
東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、野澤吉太郎です。
労働基準監督署の手続きについて書きます。
労働者を雇用する場合には、労働条件通知書などの契約関係を決める必要もあります。役所との関係では労働保険成立届を提出する必要があります。
また、労働保険料の概算保険料申告もしなければなりません。
これらは労働基準監督署宛の書類提出になります。
労働基準監督署に行く場合には、適用事業報告も忘れずに提出します。
労働保険成立届は、労働者がいない会社(使用者のみの会社)の場合には提出する必要はありません。社会保険関係の届出だけはおこない、労働保険関係の届出はしない、という場合もよくあります。
事前に、労働者名簿なども整備しておかなければなりません。
書面提出する場合には、書類を書く時間は別として、書類を受け取って簡単に中身を確認いただき、申告金額を伝えていただく、という流れで、それほど時間がかからずに終わります。
最初に労働基準監督署に行く必要があります。多くの場合(一元適用事業の場合)労働基準監督署から労働保険番号を割り振られ、その労働保険番号が分からないと、公共職業安定所(ハローワーク)での手続きができないからです。労働基準監督署の後にハローワークに行く、という流れになります。役所を訪れて手続きをする場合には、午前、午後などで分けると良いと思います。
建設業や農林漁業など、二元適用事業の場合には、現場に関する労災保険と、事務所に関する労災保険と、別々の労働保険番号が割り振られ、それぞれ別個に概算保険料申告をする必要があります。(雇用保険についても、さらに別の労働保険番号が割り振られ、別個に概算保険料申告をすることになります)
投稿者: