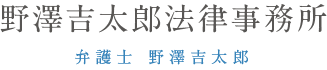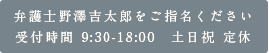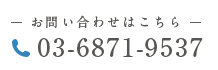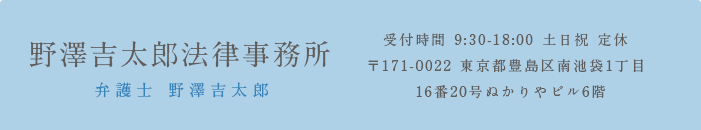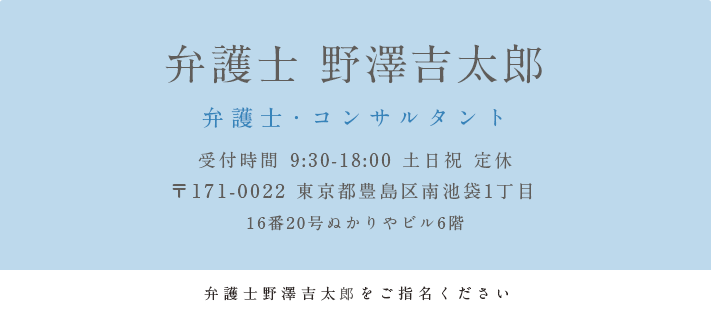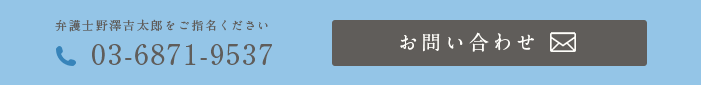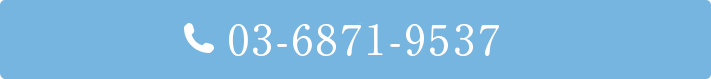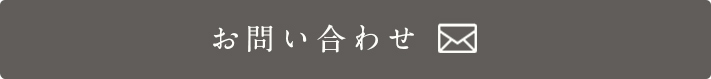東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で
主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。
事業承継に関し、後継者などの選定について書いてみます。
1 事業承継の最大の悩み事は後継者
事業承継の段取り、手続きについては、専門家に任せればよいことです。
むしろ、経営者の最大の悩みどころは、
誰に事業を引き継がせるか、
どのように引き継がせるかという点にあります。
困った経営者の方々が専門家にアドバイスを求めても
それは経営者が決めることだ、というスタンスを
取られたりすることもあるでしょう。
理屈は正しいかも知れませんが、何のためにあなたがいるんですか、
という思いを拭えないこともあるのではないかと推察します。
専門家は、実行以前の段階から悩みに真摯に向き合う必要があります。
2 後継者を指名する仕組み
客観的な立場、しがらみの薄い立場からみていくと、
上下関係からは見えてこない後継者の長所、短所が見えてくることもあります。
会社法上の委員会設置会社には、
取締役等の指名委員会という機関が存在します。
法制度上の根拠を持たなくとも、
契約や慣習を根拠として、類似の制度を創ることは十分に可能です。
指名する機関を創りたいから委員会設置会社を創る、と、
直ちに結びつけるのは飛躍だと思います。
専門家自身が権力化してしまわないよう、
人選等にも気をつけなければなりませんし、
外部関係者としての客観性を保ち続ける心遣いを
持ち続けなければなりません。
しかし、意見を求められたら
説得的な意見を言える程度にはみておかなければなりません。
外部専門家
(弁護士のみならず、コンサルタントなどにおいても同様)にとって、
難しいさじ加減が要求されるところです。
3 後継者を補佐する仕組み
ファミリー企業に親族が務められている場合は、
後継者は概ね決まっていることが多いです。
創業者のパフォーマンスを横に見ながら後継体制を構築していきます。
成功した中小企業の経営者は、圧倒的なパフォーマンスを有しています。
トップが圧倒的なパフォーマンスを持っていると、
事業の引継ぎ前に、後継者が、
独自のパフォーマンスを発揮することは、簡単ではありません。
ある程度仕方がないことです。
サポートする腹心を含めて体制を構築することが重要です。
どのような腹心を置いて乗り切るか、ナンバー2、3・・・と考えていき、
管理職にいたるまで、組織を構築する提案を行います。
ここで重要なことは、
耳の痛いことを言える人がいること、のように思います。
歯止めになる人がいない場合、少しずつ組織の歯車が狂います。
いざとなれば歯止めになる人をどこから確保するかについて、
事業承継の準備段階から考案しておく必要があります。
古参幹部に引き続き働いてもらうようにお願いすることも選択肢です。
社内の人材に適任者がいればよいですが、
存在しないことも多いと思われます。
社内にいなければ外部から招聘できるか否かを検討し、
待遇がネックになるようであれば改善を提案します。
4 人間を観察し、信頼関係構築の橋渡しをする
後継者、これを補佐するナンバー2、3・・・を選定していく際には、
関係者を絶えず観察し、コミュニケーションをとり、
創業者と後継者の信頼関係の構築の橋渡しをすることも重要です。
後継者と思い定めた人が、ふとしたきっかけで、
態度を豹変させることはあり得ます。
そのような場合には、信頼できる関係者を増やしておくことが、
事業承継のリスク軽減に役立ちます。
何かトラブルのタネがあったとしても、
あの人に迷惑を掛けるから裏切れないな、
と後継者に思わせるような専門家がいることは、
トラブルの防止に役立つことと思います。
書き尽くせない話ですが、この程度にしておきます。
弁護士野澤吉太郎について
■「企業法務/事業承継」についてのその他の関連ブログはこちら
企業法務/事業承継(1)
企業法務/事業承継(3)
■「企業法務/事業承継」についてのHPの詳しい情報はこちら
■相談・問い合わせはこちらをクリック■
--------------------------------
野澤吉太郎法律事務所
弁護士 野澤吉太郎(のざわ きちたろう)
〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番20号ぬかりやビル6階
「池袋駅」西武南口徒歩1分
TEL 03-6871-9537
HPはこちらをクリック